坂本 彩香 監修
ブロバスケットボールチーム 熊本ヴォルターズ トレーナー
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校アスレティックトレーニング専攻 学士を卒業。
「BOC-ATC (米国アスレティックトレーナー資格認定委員会公認アスレティックトレーナー)」という、
アメリカでは准医療従事者として認定され国家資格の立ち位置にあり、日本国内での保有者はわずかしかいない資格を取得。
現在は熊本ヴォルターズのトレーナーとして、選手のサポートに従事。
「足のむくみにはどんな病気がある?」「原因は?」とお考えの方へ。足に起こるむくみには様々な原因が考えられるため、まずは病院受診がおすすめです。本記事では、足がむくんでいるときに考えられる6つの原因や対処法を解説します。

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。
再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。
さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。
おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。
ここでは「足のむくみって病気?」とお悩みの方へ、考えられる6つの原因を解説します。
解説するものは1つの例であるため、気になる方は病院を受診してみましょう。
心不全は、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、症状が段々悪くなることによって生命を縮める病気です。
心不全によるむくみの原因は「心臓から腎臓に流れる血液が少なくなって尿の量が減った結果、水分が体内に貯留するから」と考えられています。
また、むくみは足の甲やすねのあたりにあらわれ、体重増加も見られます。
腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な塩分を尿として体外へ排出する役目があります。
腎臓病によるむくみの原因は「水分を十分に排泄できなくなることによって、体内に余分な水分が溜まってしまうから」と考えられています。
また、むくみは左右対称にくるぶし付近からあらわれ、むくんでいる部分を指で10秒以上押さえると指の跡がへこんだまま残ります。
肝臓は「血液中を流れるタンパク質を作る」「有害物質の解毒・分解」「食べ物の消化に必要な胆汁の合成・分泌」の役目を持っています。
肝臓病によるむくみの原因は「肝機能の低下によってタンパク質が減少し、血液の成分割合が変化した結果、血液の成分が血管外へ染み出してしまうから」と考えられています。
また、むくみは腹や手足にあらわれ、腹水と呼ばれる合併症に繋がりやすくなります。
深部静脈血栓症は、足から心臓へ帰る静脈へ何らかの原因によって血栓ができて詰まってしまう病気です。
深部静脈血栓症によるむくみの原因は「血栓によって静脈が心臓へ戻りにくくなるから」と考えられています。
また、むくみは片側だけにあらわれ、太ももやふくらはぎが太くなることや、むくみが強いと痛みや赤み、放置していると皮膚が茶色に変色する場合もあります。
糖尿病は、膵臓から出るホルモン「インスリン」が十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖が増える病気です。
糖尿病によるむくみの原因は「血糖の高い状態が続いて老廃物をろ過する機能が衰え、状態が進行することによって血管外に水分が染み出るようになるから」と考えられています。
また、むくみは足から体全体にあらわれますが、この他にも様々な症状が生じます。
下肢静脈瘤は、足の静脈が太くなってこぶ状に浮き出て見えるようになった状態です。
下肢静脈瘤によるむくみの原因は「静脈内にある逆流防止弁と呼ばれるものが壊れ、足の静脈内に血液が滞り、静脈の内圧が高くなった結果、血液中の水分が毛細血管外へ染み出て皮膚下の脂肪組織に溜まってしまうから」と考えられています。
また、むくみはほとんどのケースで片方の足にあらわれます。
本記事で解説した病気以外にも、足にむくみが生じる病気は複数考えられます。
そのため「足にむくみがある」という場合は、安易に自己判断せず、病院受診が大切です。
次は、病気以外で足のむくみがあるときに考えられる原因を6つ解説します。
「病気ではないけれど、むくみに悩んでいる」という方はぜひ参考にしてください。
長時間の立ちっぱなしや座りっぱなしによって下半身にあるリンパの流れが滞ると、体内の老廃物がふくらはぎに集まり、むくみが生じやすくなります。
定期的に足を動かしたり、立ち上がったりするなどリンパの流れが滞らないよう意識するだけでもむくみの改善につながるでしょう。
食生活の乱れや、塩分の摂りすぎは足のむくみを引き起こしやすくなります。
例えば、ビタミンB1が不足すると代謝機能がうまく働かなくなったり、タンパク質が不足すると毛細血管が水分をやりとりする力が低下します。
加えて、人間の体には体内の塩分濃度を一定に保とうとする働きがあるため、塩分を摂りすぎると「塩分濃度を薄めなければ」と体内に水分をためこみやすくなるのです。
そのため、豚肉などに含まれるビタミンB1や「肉」「魚」「豆腐」などに含まれるタンパク質を食事にバランス良く取り入れ、塩分摂取量も意識することが大切です。
運動不足によってふくらはぎをあまり動かさない生活が続くと血液が足に溜まり、うっ血してむくみを引き起こしやすくなります。
また、血液を心臓に戻す役目も果たしているふくらはぎの筋力が低下すると血液を送る力が弱まり、血液中の水分が皮膚や皮下脂肪にたまりやすくなります。
そのため、適度な運動と筋力維持はむくみ予防改善に大切なのです。
妊娠や月経周期によるホルモンバランスの変動によってむくみやすくなることもあります。
例えば、妊娠中は生理的に細胞の中へ水分がたまりやすく、徐々に子宮が大きくなると下半身の血行が滞ってしまうため、結果的にむくみが生じます。
また、月経周期は血流を調整する自律神経が不安定になり、むくみやすくなるのです。
そのため、バランスの良い食事やマッサージ、ストレッチなど体の状態に適した対処法でむくみを予防改善できるよう意識することが大切です。
アルコールを飲むと血管が拡張するため、血管から血管外へ水分が漏れ出してむくみやすくなることも考えられます。
加えて、飲酒のおつまみに塩分が高い食べ物を摂取すると更にむくみやすくなり、高血圧を発症するリスクも高まるため、注意が必要です。
どうしても飲酒とおつまみが楽しみでやめることができないという方は、病院を受診して適切な飲酒量とおつまみとしてどのようなものが良いかを相談してみましょう。
薬剤性浮腫とは、薬の副作用として一時的にむくみがあらわれることです。
むくみを引き起こす代表的な薬の例としては「胃腸薬」「高血圧の薬」「糖尿病の薬」「消炎鎮痛剤」などが挙げられます。
ただし、これらの薬を服用すると必ずむくみが生じるわけではありません。
薬を服用していてむくみがあらわれたのかな?と感じた場合でも、まずは病院を受診して医師に相談することが大切です。
次は、日常的に行える足のむくみを解消する方法を4つ解説します。
「最近、むくみがあって悩んでいる」という場合、自己判断で原因を特定し、対処することは控えてまずは病院を受診するべきでしょう。
本記事で解説したとおり、むくみの原因は様々です。
仮に、病気以外が原因でむくみを生じていたとしても、医師の診察やアドバイスによってむくみの改善予防につなげられるため、長期的に続く場合は病院を受診しましょう。
足のむくみ予防改善には適度な運動やマッサージが有効です。
ふくらはぎに力が入り、筋肉のポンプ作用を働かせるウォーキングや散歩はむくみ予防につながりますし、むくみが辛い場合は仰向けになって足を動かす運動もおすすめです。
また、マッサージに関しては「手で足をなでるようにしてリンパ液の流れを改善する」という点を意識するとリンパ液によって老廃物を運搬し、むくみ解消につながります。
ビタミンB群は、水分代謝を活発にする働きがあるため、むくみの予防や改善におすすめです。
また、ミネラルの1つであるカリウムには細胞内液の浸透圧を調整し、一定に保つ働きがあるため、こちらもむくみの予防や改善策として積極的に摂取したい成分でしょう。
他にも「スイカ」や「きゅうり」「冬瓜」などウリ科の食べ物もむくみの予防改善に効果が期待できると考えられるため、ぜひ1日の食事に取り入れてみてください。
「長時間立ちっぱなし、座りっぱなしの仕事でむくみが辛い」という方は、市販で購入できるフットケア商品もむくみの予防と改善に活用できます。
また「いつもフットケア商品を活用しているけれどむくみが辛い」という方は、医師の指導を受けて使用する弾性ストッキングも検討してみてください。
弾性ストッキングについて病院を受診する際は、医師の診察や問診の際に「利尿剤の処方」や、適切な科を紹介してもらうなど気になる点を相談してみても良いでしょう。
次は、足のむくみが気になるときは何科を受診するべきかを解説します。
足のむくみが病気か気になる際、受診するべき科は「むくみの具体的な症状」や「他に何らかの症状がないか」などで判断します。
そのため「何科を受診するべきかわからない」という場合は、まず内科を受診してみても良いでしょう。
内科は「内臓」「血液」「神経」などを専門とする科です。
カゼや頭痛、腹痛に胃腸炎など一般的によくある症状や疾患に対応しています。
また「高血圧」や「糖尿病」などにも対応しているため、むくみ以外にも「最近めまいや肩こりがする」「喉が渇く」などの症状がある場合、内科を受診して相談してみましょう。
循環器内科は「心臓の病気」や「大動脈」および「末梢血管」などを専門とする科です。
心臓に関わる疾患や、血管に関わる疾患に対応しています。
むくみ以外にも「息切れがする」「突然脈が速くなる」などの症状がある場合、循環器内科を受診して相談してみましょう。
血管外科は「心臓と脳以外の全身にある血管」を専門とする科で、下肢静脈瘤クリニックはその名のとおり「下肢静脈瘤」を専門としていますす。
下肢静脈瘤の治療は主に血管外科で行われることもありますが、地域によっては下肢静脈瘤クリニックの方が認知されているケースもあります。
むくみ以外にも「足の血管が浮いてこぶ状のものができている」などの症状がある場合、いずれかの科・クリニックを受診して相談してみましょう。

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。
再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。
さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。
おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。
本記事では、足にむくみがあるときに考えられる6つの原因と対処法を解説しました。
むくみの原因は様々であるため、何が原因かわからないという場合は病院受診が大切です。
また、病気以外が原因の場合は日常的に行える対処法で辛いむくみを予防、改善しましょう。
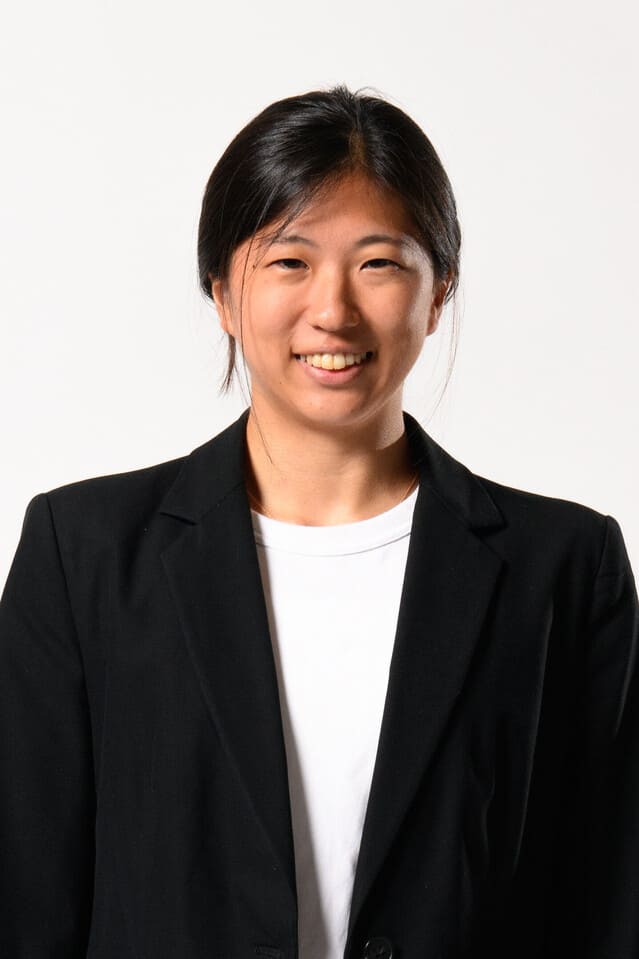
坂本 彩香 監修
ブロバスケットボールチーム 熊本ヴォルターズ トレーナー
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校アスレティックトレーニング専攻 学士を卒業。
「BOC-ATC (米国アスレティックトレーナー資格認定委員会公認アスレティックトレーナー)」という、
アメリカでは准医療従事者として認定され国家資格の立ち位置にあり、日本国内での保有者はわずかしかいない資格を取得。
現在は熊本ヴォルターズのトレーナーとして、選手のサポートに従事。