坂本 彩香 監修
ブロバスケットボールチーム 熊本ヴォルターズ トレーナー
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校アスレティックトレーニング専攻 学士を卒業。
「BOC-ATC (米国アスレティックトレーナー資格認定委員会公認アスレティックトレーナー)」という、
アメリカでは准医療従事者として認定され国家資格の立ち位置にあり、日本国内での保有者はわずかしかいない資格を取得。
現在は熊本ヴォルターズのトレーナーとして、選手のサポートに従事。
「足の筋肉を鍛えると、どんなメリットがあるの?」とお考えの方はいませんか?足の筋肉は、スムーズな歩行や、何歳になっても元気な足腰を維持するために大切です。本記事では、足の筋肉「部位」で考える鍛えるメリットや、5つの筋肉をつける(鍛える)方法を解説します。

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。
再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。
さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。
おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。
足には多くの筋肉があり、耳にした経験があるものから「どの部位?」とあまり知られていない筋肉まで様々です。
場所 |
鍛えるメリット |
|
|---|---|---|
大腿四頭筋 |
太もも前側の筋肉 |
|
ハムストリングス |
太もも裏側の筋肉 |
|
下腿三頭筋 |
ふくらはぎ |
|
内転筋 |
太ももの内側 |
|
前脛骨筋・後脛骨筋 |
|
|
腓骨筋群 |
膝から下の外側 |
不意に起こりやすい足首の捻挫予防 |
長趾屈筋・長趾伸筋 |
|
|
長母趾伸筋・長母趾屈筋 |
|
スムーズな歩行や足関節にかかる負荷を軽減 |
ここでは、足の筋肉の名前「部位」ごとに鍛えるメリットを解説します。
大腿四頭筋は、太ももの前側にあり、主に膝関節を伸ばす機能をつかさどる筋肉です。
「大腿直筋(だいたいちょっきん)」「内側広筋(ないそくこうきん)」「外側広筋(がいそくこうきん)」「中間広筋(ちゅうかんこうきん)」の4つから成り立っています。
大腿四頭筋は、足を伸ばす際に働く筋肉で「歩く」「立ち上がる」など下半身の主な動作にほぼ関わっているため、鍛えることによって膝関節にかかる負担を軽減できます。
年齢を重ねると下肢(足)の筋力が衰え、少しの段差でつまずいて転倒してしまうリスクが増加することから、元気な足腰を維持するためにも大腿四頭筋は非常に大切な筋肉です。
ハムストリングスは、おしりの付け根から太ももの裏側、太ももから膝裏周辺にある「大腿二頭筋(だいたいにとうきん)」「半膜様筋(はんまくようきん)」「半腱様筋(はんけんようきん)」の3つを総称した筋肉です。
ハムストリングスは太ももの裏側にある大きな筋肉で、筋肉低下によって弱くなったり柔軟性が不足したりすると膝の屈伸力の低下につながります。
ハムストリングスを鍛えることによって、下半身を安定させる効果が期待できるほか、日常生活のちょっとした動作に対する膝や腰への過度な負荷を軽減する効果も期待できます。
下腿三頭筋は、ふくらはぎを形成する「腓腹筋(ひふくきん)」「ヒラメ筋」の2つから成り立つ筋肉です。
地面をキックしたり、足首を固定したりする際にも使われている筋肉で、筋力低下を起こすとつま先が地面や段差に引っかかったりしやすくなります。
下腿三頭筋を鍛えることによって「歩く」「走る」「ジャンプ」などの動作をサポートしてくれるほか、地面や段差につま先が引っかかって起こる転倒リスクを軽減します。
内転筋は「恥骨筋(ちこつきん)」「短内転筋(たんないてんきん)」「長内転筋(ちょうないてんきん)」「大内転筋(だいないてんきん)」の4つから成り立つ筋肉です。
内転筋は、骨盤の安定やO脚を改善するためにも重要な筋肉で、筋力低下が起こると「膝関節に負荷がかかる」「骨盤が不安定になって腰痛の原因になる」などの状態が生じます。
内転筋を鍛えることによって、バランス力強化や膝痛・腰痛の予防・改善につながります。
前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、スネの外側にあり、歩行時によく使われる筋肉です。
また立った状態でバランスを維持する役割を担っているため、前脛骨筋を鍛えることによって、スムーズな歩行や転倒リスクの軽減につながります。
次に、後脛骨筋(こうけいこつきん)は、足関節の内側・内くるぶしの後方から下方を通っている筋肉です。
足首を動かすことで足裏にかかる荷重バランスを調整し、足や体を安定させたり、着地時の衝撃を和らげる役割を担っています。
後脛骨筋を鍛えることによって、足の裏にある土踏まずが潰れて平らになる扁平足や「歩く」「走る」などの動作時にかかとを中心に足裏が痛む足底腱膜炎の予防につながります。
腓骨筋群(ひこつきんぐん)は「長腓骨筋(ちょうひこつきん)」「短腓骨筋(たんひこつきん)」「第3腓骨筋(だいさんひこつきん)」の3つから成り立つ筋肉です。
腓骨筋群は、足裏が内側を向く動きを行う際に不安定な足首を安定させる働きを担っており、スポーツなど活動時に発生しやすい足首の捻挫を防ぐ役割を持っています。
腓骨筋を鍛えることによって、不意に起こりやすい足首の捻挫予防につながります。
長母趾伸筋は前脛骨筋と長趾伸筋に覆われた筋肉です。
長母趾伸筋は、親指をまっすぐにしたり、歩行の際につま先を持ち上げるなどの働きを補助しており、鍛えることによって、地面や段差につま先が引っかかって起こる転倒リスクを軽減します。
次に、長趾伸筋は膝下からすねの外側に沿って足の指まで付いている筋肉です。
足首や足の指を反る働きをしており、歩行時によく使われる筋肉です。
長趾伸筋を鍛えることによって、長趾屈筋と同じくスムーズな歩行をサポートし、予期せぬ転倒リスク軽減につながります。
また、長趾屈筋と長趾伸筋に似た筋肉に「長母趾伸筋」「長母趾屈筋」があります。
長母趾伸筋(ちょうぼししんきん)は、足首を曲げ、つま先が上にあがる動きや親指を持ち上げたりする働きを担う筋肉です。
反対に、長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)は、足関節を曲げたり、親指を下に下げたり足関節を内側に曲げる動きを補助しています。
あまり耳にしない筋肉ですが、スムーズな歩行や足関節にかかる負荷を軽減させるために大切な筋肉であるため、覚えておくと良いでしょう。
次は、足の筋肉をつける(鍛える)5つの運動方法を解説します。
運動方法と動画をあわせて解説しているものもありますので、ぜひ参考にしてください。
スクワットは「大腿四頭筋」「ハムストリングス」「大臀筋(おしりの筋肉)」を鍛えられる運動方法です。
スクワットによって足、特に下半身の筋肉を鍛えることは、脚力を向上させ、転倒リスクの軽減や日常生活での動作改善につながります。
【スクワットのやり方】
最初は1回でも太ももに効いている感覚を感じられます。
記載している回数より少ないから効果が出ないというわけではありませんので、ご自身ができる範囲から始めてください。
【ハーフスクワットのやり方】
ハーフスクワットは、通常のスクワットとは異なり「腰を深くまで下げる必要がない」ため、比較的筋力に不安を感じている方でもおこないやすい運動方法です。
ハーフスクワットであっても、通常のスクワットと得られる効果はそこまで変わらないというデータもあるため、スクワットができるか不安な方はこちらから始めてみましょう。
もも上げは「大臀筋」などの筋肉を鍛える運動です。
今回は椅子に座っておこなえるもも上げのやり方を解説します。
【もも上げ運動のやり方】
座った状態のもも上げは、転倒による怪我のリスクもなく、自分のペースでおこなえます。
グッドモーニングは、ハムストリングスを鍛えられる運動です。
【グッドモーニングのやり方】
ハムストリングスを伸ばす際は、痛みを感じるまで伸ばすと筋を痛める可能性もあるため、痛みを感じる手前を維持しましょう。
こちらのエクササイズは、管理栄養士さんによる下半身を鍛えるエクササイズです。
【エクササイズのやり方】
【筋トレ】高齢者・運動苦手でもできる!下半身を鍛えるエクササイズ(1)〈管理栄養士による健康レッスン!〉
それぞれの運動後には30秒間の休憩として足踏みを入れて行います。
1日5分で運動不足になりがちな高齢者の方や、運動が苦手という方でも気軽に行えます。
こちらはフレイルと呼ばれる「病気ではないけれど、年齢とともに筋力や心身の活力が低下して介護が必要になりやすい状態」を予防する運動です。
【フレイル運動のやり方】
【高齢者・シニア向け】寝たまま10分で介護・フレイル予防運動~太もも・ふくらはぎ・おしりを鍛えよう!~
寝ながら行える運動ですので、体力に自信がない方でも気軽に行えます。
まずは動画を見ながら自分のペースで行ってみましょう。

歩みのゼリーは、中高年の「歩く力の向上」に役立つとともに、お腹まわりの「脂肪を消費・減少」させ、年齢に負けないしなやかな体づくりをサポートする、機能性表示食品です。
再春館製薬所が漢方の知見を活かし、機能性関与成分である「ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン」の他、高麗人参の中でも特に希少で品質の良い「長白参エキス」を配合。
さらに、筋肉づくりに欠かせない必須アミノ酸「バリン」「ロイシン」「イソロイシン」に加え、スーパーアミノ酸と称される「シトルリン」や「アルギニン」によって、ハリのある活動的な毎日をサポートします。
おいしくさわやかな紅茶風味のスティックゼリーで、1本食べることで普段の「家事」「仕事」「散歩」といった行動を、効率的に「歩く力の向上」と「お腹の脂肪対策」につなげます。
本記事では、足の筋肉の名前「部位」から解説する足を鍛えるメリットや、簡単に行える足の筋肉をつける(鍛える)5つの運動法を解説しました。
足は、どの筋肉もスムーズな日常生活を送るために大切です。
それぞれの筋肉を鍛えるメリットを学び、解説した動画で足の筋肉を鍛えていきましょう。
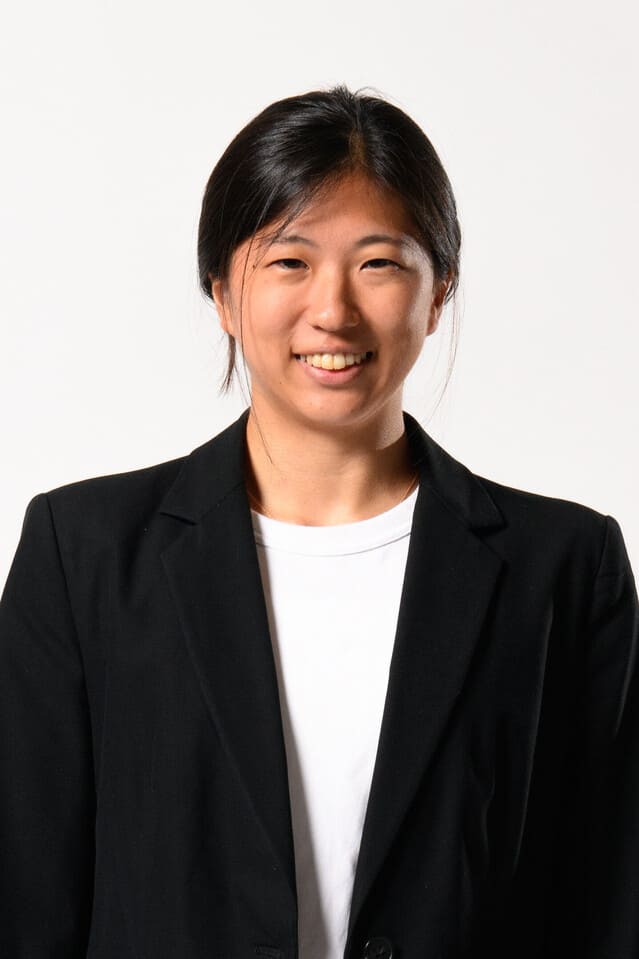
坂本 彩香 監修
ブロバスケットボールチーム 熊本ヴォルターズ トレーナー
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校アスレティックトレーニング専攻 学士を卒業。
「BOC-ATC (米国アスレティックトレーナー資格認定委員会公認アスレティックトレーナー)」という、
アメリカでは准医療従事者として認定され国家資格の立ち位置にあり、日本国内での保有者はわずかしかいない資格を取得。
現在は熊本ヴォルターズのトレーナーとして、選手のサポートに従事。