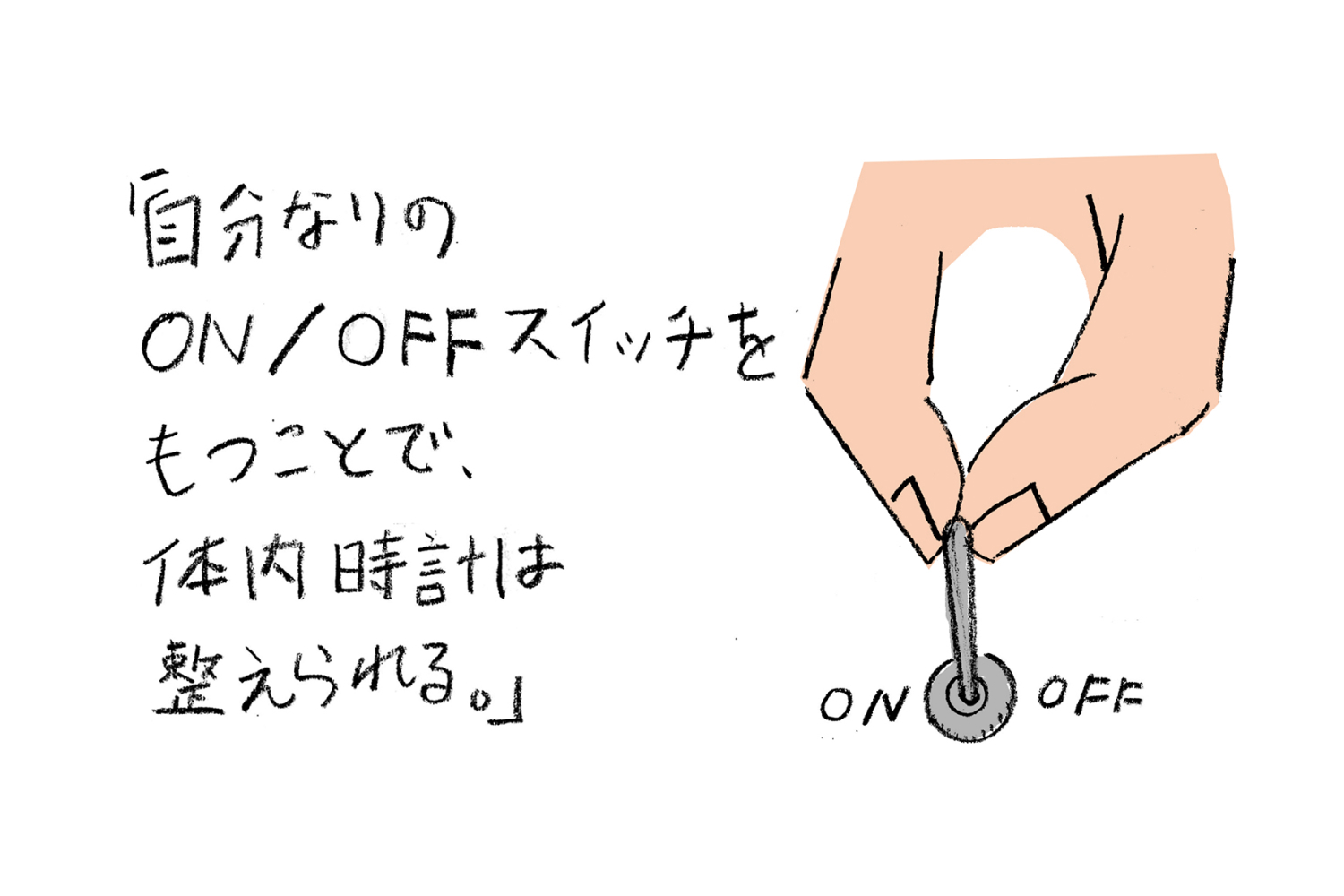実は、体内時計は
もともとずれている?
――前回の「いつ、何を、食べるか(時間栄養学)」編で、「体内時計」のお話が出ましたけれど、そもそも、体内時計っていったいどういう仕組みなんですか?
地球の自転周期に合わせて、24時間周期のリズムをつくるためのプログラムです。
例えば体温やホルモン分泌などは、約24時間周期のリズムを示すことが明らかになっています。
私たち人間の体の中には、「朝になると自然に目が覚めて、夜は休息に向かう」という体内時計のリズムが、古くから備わっているのです。

――よく「体内時計を整えよう」っていわれますよね。不規則な生活をしていると、この体内時計が乱れてしまうということでしょうか。
そうですね、体内時計が乱れるというのは、いわゆる時差ボケのような状態です。体内の臓器や組織がうまく働かなくなり、体調が悪くなります。生活習慣病のリスクが高まりますし、美容にも悪影響がありますよ。
でも、それだけではないのです。実はこの体内時計、1日24時間ではなく約24時間10分の周期で動いているんです。
――ええっ、そうなんですか? もともと時計が狂っている?
それを24時間の周期に合わせるために、日々体内時計をリセットすることが必要です。
そのために重要なのが、「光」と「食事」の刺激です。

――光って日光のことですか? そういえば、海外旅行に行った時に「時差ボケを解消するには、朝日を浴びるといい」って聞いたことがあります。
その通りです。私たちの体の中には、二つの時計があります。脳にある「中枢時計」と、体の臓器の「末梢(まっしょう)時計」です。
まず朝日を浴びることで中枢時計が朝を認識し、スイッチをOFFからONに。
次に、朝食をとることを合図に、末梢時計のスイッチがONになります。
この二つのリズムが同調することで、脳と体はうまく動き始めるのです。
自分に合った生体リズムを
デザインしてみよう
――なるほど。そうやって毎日体内時計を調節しているんですね。ということは、日が沈んだらスイッチをOFFにするために、本当はもう休んだ方がいいの? うーん......。
昔の人は、日の出・日の入りに合わせて寝起きする生活が無理なくできていました。
でも現代ではそうはいきませんよね。
日が沈んでからも仕事や家事、育児に追われて、ONが続きっぱなしという人も多いでしょうし、勤務時間が遅いから、朝はゆっくり起きるという人もいるでしょう。
――つまり、私たちの体内時計は狂いっぱなし......?
いえいえ、ちょっと工夫をするだけで、体内時計の調節は可能なんですよ。
コツは、時間を周りに合わせ過ぎないこと。
自分の時間軸に合わせて、ON/OFFを切り替えることです。
それによって、体内時計に合わせて刻まれている「生体リズム」も安定させることができます。
生体リズムとは、一定の周期で体に起こる変化のこと。
例えば、朝から昼にかけては血圧や脈拍などが高くなり、夜になると低くなるのも生体リズムによるものです。
――自分なりの時間軸をつくるってことですか? どうやって?
そのためにはやはり、「光」と「食事」を味方につけましょう。
まず光は、遮光カーテンや照明を利用するという方法があります。
夜型の仕事の人は、遮光カーテンで朝日を遮るのも手ですね。
また、以前もお話ししたように、照明を利用して、活動する時間は明るい光、夜は穏やかで温かみのある光にすると、ON/OFFが切り替えやすくなりますよ。

――なるほど! 無理やり行動をお日さまに合わせなくてもいいんですね。それならできそうな気がします。
食事についても、朝食の時間が遅い人は、昼食の時間もずらして遅くするなど、自分なりの時間軸を守ること。
いわば、「自分で自分の生体リズムをデザインする」感覚です。
――それができたら最高ですね!
「何時までに食べなきゃ」「何時になったから寝なくちゃ」という縛りから解放されたら、もっと自分らしく毎日を楽しめそう。さすがの益軒さんも、そんなことができるとは思いつかなかったかも。
ぜひ、自分の生活に合わせて生体リズムを整える意識を持って過ごしてみてください。
音楽や香り、入浴の仕方などもスイッチの切り替えに役立つと思いますよ。
――はい。私はこれからもうひと仕事あるので、ミントの香りが強いガムをかんでスイッチを入れます!
更新