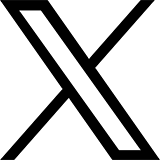「うちのばあちゃんの名前は、つる」
「私のところは、はなっていうんだよね。それなら、新しい雑誌は『つるとはな』にする?」
箱根の温泉場での他愛ないおしゃべりから、2014年、「人生の先輩に聞く」というテーマの雑誌が生まれました。
「おばあちゃん、おじいちゃん」ではなくて、一人一人違う名前で、違う人。だから、敬意を込めて先輩と呼ぼう。当時59歳だった編集者・岡戸絹枝さんと編集仲間は、取材対象を70歳以上の人たちに絞りました。

創刊号を開くと、『つるとはな』の誌名にちなんで、2文字の名前を持つご婦人たちが登場。92歳「ます」さんと90歳「りん」さん姉妹が手をつないで語る昔話や、街の片隅でおでん屋を切り盛りする「つね」さんの心がけ。
そのほか多くの先輩たちの来(こ)し方(かた)やいまの暮らしぶりが、いきいきとした写真と文章で描き出されています。それぞれの人生が"私の物語"なのであり、何歳になろうとも日々新しく紡がれていることに胸がじんわりと温かくなります。
雑誌編集の道を40年以上歩んできた岡戸さんは、大手出版社でおしゃれやカルチャーを発信する『Olive』の編集長を務めた方です。
2002年には『ku:nel(クウネル)』を創刊。芸能人でも成功者でもない、あたりまえの生活を丁寧に過ごす人を紹介する雑誌は当時珍しかったため、社内では「売れないのでは?」とも囁(ささや)かれましたが、「こういうものが読みたかった」と熱心な読者がつきました。
創刊した頃、年上の人たちに
尋ねていたある質問
50代半ばに出版社を辞めた岡戸さんは、なぜ人生の先輩に話を聞こうと思ったのでしょう。
「4年くらいぶらぶらしながら、新しく雑誌をつくるならどんな人に会いたいか、考えてたんですね。これまでの取材を振り返ると、経験を積み重ねた年上の人たちの話は味わい深かった。人間の層の厚みが違うなあって。じゃあ、お元気で自立かつ自律されている年配の人たちに会いに行こうと」
岡戸さんが言う、自分で立ち、自らを律する人の例を挙げるなら、日々楽しく暮らす工夫がある人。好きなことや勉強、仕事を自分のペースで続けて今日を溌剌(はつらつ)と生きる人。ページをめくれば、そんな人たちの日常が笑い声や口癖とともに立ち現れます。

朝目が覚めて、「今日は何食べようかしら」と台所に立つ料理家の心持ち。麻雀とうなぎに目がなくて、朝夕にはそっと祭壇に手を合わせる100歳の毎日。
岡戸さんが大好きな宇宙飛行士・向井千秋さんの「おかあちゃま」と一緒に散歩しながら聞いた、米国珍道中の思い出。最愛の伴侶に先立たれ、寂しさが織り込まれた暮らしもありのままに描かれています。

「『つるとはな』を創刊した頃は、ご自身はどんなふうに人生の終わりを迎えたいですかと、皆さんに聞いてたんです。私はそれを知りたかったから」
人は年齢とともに、「この先」に漠とした不安を抱え、明日をより有意義に生きようと力みがちです。でも、「よその国のレイディーズ」というコーナーに登場するアイルランドの姉妹は言いました。
「起きてもいない未来をおそれるのは無意味よ。(中略)私たちにできるのは日々起きる現実をただ受け入れて、その中でベストを尽くすことだけ」
この言葉は、「いまあるものだけでじゅうぶん幸せ」という満ち足りた気持ちがあればこそ、すっと出てくるのかもしれません。こうした先輩たちの顔つきや言葉を眺めるうちに、「もう年齢は気にしなくていいや」と、勇気りんりん走り出したくなるような力が湧いてくるのです。
岡戸さんは、取材を続けるうちに、「終わりの迎え方なんて聞かなくてもいいな」と思うようになったそうです。
つくる雑誌は変わっても
伝えたいことは変わらない
さて、そんな『つるとはな』にどんな反響があったのか。創刊号は増刷するほどの人気を集め、2号、3号も書店で積み上げられるほどに支持されました。
「とはいえ、隙間みたいなジャンルの雑誌だから、販売部数はさほど多くないんですよ」
さまざまな事情があって、ほぼ年1回の発行は5号で見合わせ。
「売れることを優先するなら、もっと受けのいい内容を増やすとか、すべきことがあるのに。私ったらやりたいことしかしてこなかったから。自分が読みたいページ優先だったんです」と岡戸さんは言い切ります。
2024年の秋、7年ぶりに最新号を出版したのは理由があるのでしょうか。
「このまま終わったら、私、中途半端じゃない? って思っただけ。ふと見渡せば、そういう時代になったんでしょうか、80代でもお元気な方がたくさん。70歳なんて、もう私だもん!」

忘れられないエピソードは? と聞いてみました。すると、94歳の現役飛行機乗りの髙橋淳さんが若い頃を語った時だと教えてくれました。「戦時中もいまと同じように日常があったんだ。こういう言葉を伝えたい」と思ったそうです。
先輩たちの声を聞くことで、ご自身が年齢を重ねることへの考え方は変わってきたのでしょうか。
「先輩の言葉は私の身に入ったんでしょうかね。自分が変わったのかどうか、いまはわかりませんね。これから先、ふとした時に気づくのかも」

岡戸さんは、自分に確かめるように慎重に言葉を選びました。一方で、つくる雑誌は変わっても、伝えようとしてきたことは変わらないと言います。
「人は一人。小さな家庭から社会まで全て、自らで立ち、律して生きている人の集まりですよね。一人で暮らそうと一人、二人で暮らそうと一人」
最新号で、歌人の馬場あき子さんは「生きている限り、人間は寂しい。寂しくない人っているの?」と語りました。
「馬場さんの言葉は、いまの私の心に染みることばかりでありがたかった」と岡戸さんは振り返ります。
難しいと思っていた短歌が、なぜか心にすっと流れ込んでくる。そんな変化こそ、人生の味わいなのかもしれません。
更新