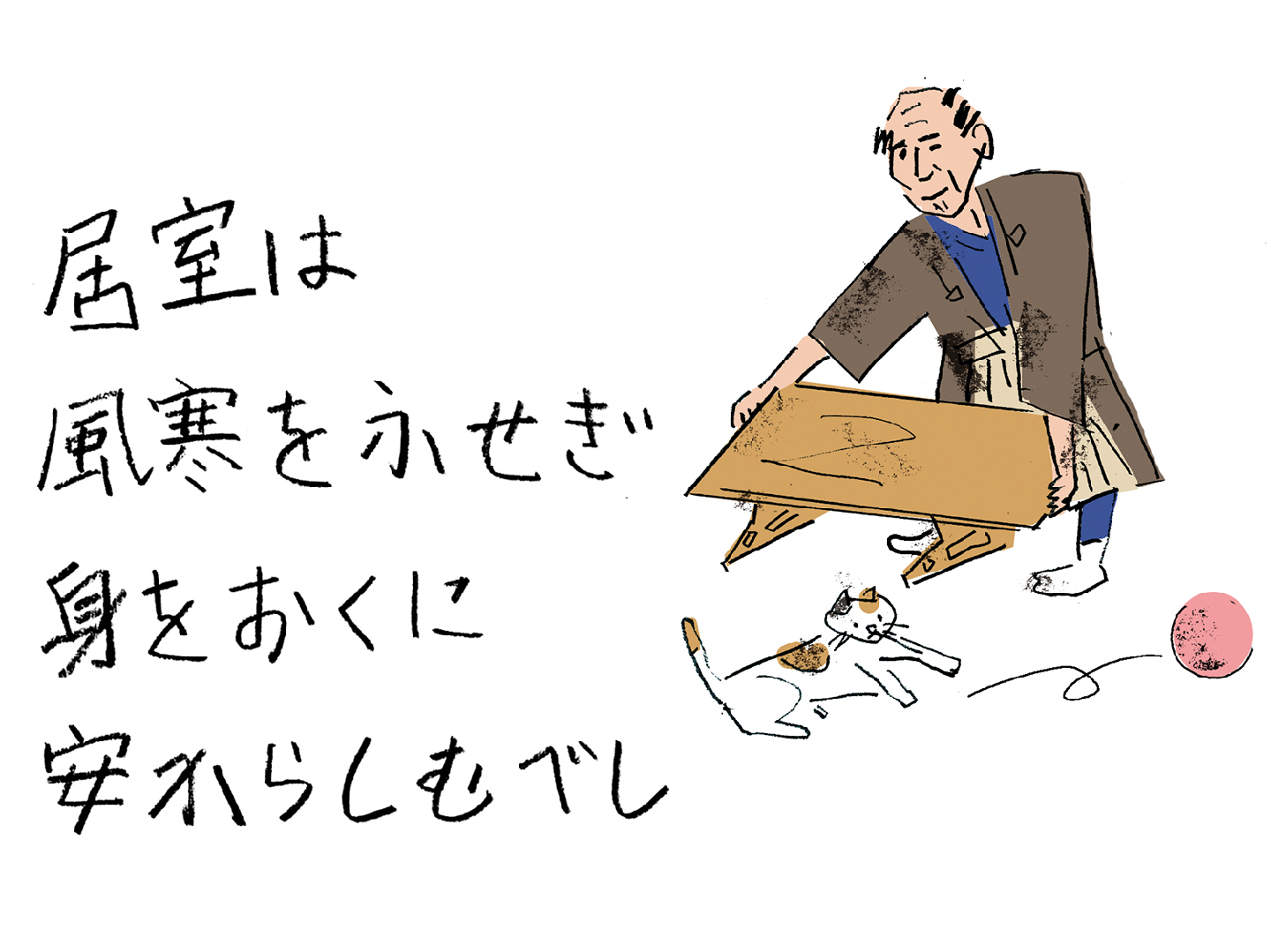家の居心地も
「養生」の鍵に
臼井さんに質問です。人は1日のうち、どれくらいの時間を家の中で過ごしていると思いますか?
――えっ、突然ですね! うーん、仕事に出かけたり、外で食事したりすることも多いから......。睡眠時間プラス数時間と考えると、平日は12時間くらいかな?
実は、日本人の平均在宅時間は1日16時間58分(2021年総務省「社会生活基本調査」より)。思ったより長いでしょう?
――ええ。意外と家で長く過ごしてるんですね。
「人生100年時代」の言葉に当てはめると、約70年にも相当する長さとなります。
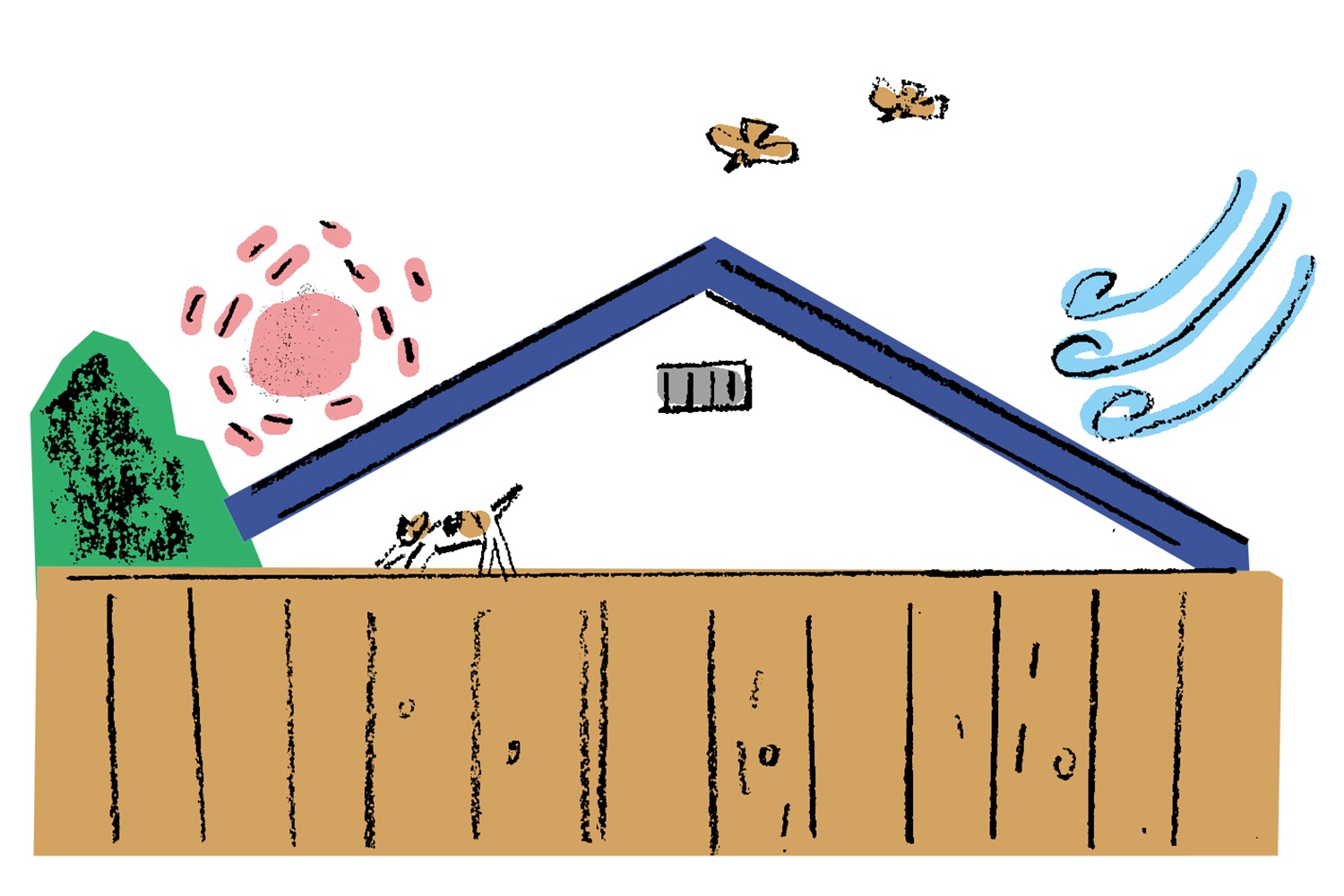
最近では、感染症によるリモートワークの増加とか、猛暑や豪雨といった"気候危機"により、さらに在宅時間が増える傾向にありますし、家の居心地がいいかどうかは人生において重要な問題です。
――なるほど。住まいによっても健康になったり、不健康になったりするということですね?
はい。益軒さんも『養生訓』の中で、何度か「住まいが健康に与える影響」について述べているんですよ。
そのうちの一つが、「居室は風寒をふせぎ身をおくに安からしむべし」という言葉。「居間は寒風を防いで、気持ちよく安らかに住めるように工夫すること」という意味です。環境を快適にすることが、「養生の補助となる」というのです。
――でも益軒さんの時代には、エアコンもないし、窓は二重サッシでもないから、冬は寒く、夏は暑くて大変だったのでは......?
と思うでしょう? でも昔から日本人の住居には、快適な室内環境をつくるさまざまな工夫がなされていました。
例えば建物の木材や土壁、畳などの自然素材は、室内を夏は涼しく、冬は暖かく保つことができる上、湿気を吸収したり放出したりすることができます。
さらに、廊下や土間をつくることで風通しをよくしていたんです。
――へぇ~。昔ながらの日本の家には、そういう機能があったんですね。暑さや寒さを防ぐ以外には、どんな工夫があったんですか?
例えば障子や格子窓を通して自然光を入れることで、明るすぎない穏やかな空間をつくり出していました。光と健康の関係については、第2回「夏の睡眠習慣編」や、第4回「体内時計の整え方編」でもお伝えしてきましたよね。
また、大きな掃き出し窓と縁側があることで、内と外がゆるやかにつながり、近所の人とコミュニケーションがとれて、自然の風景を楽しむことができていたのです。

――コミュニケーションとか自然の風景とかって、健康に関係あるんですか?
大いに関係あるんですよ。
「孤独」や「孤立」がさまざまな病気のリスクを高めることは、研究により明らかになっていますし、自然との触れ合いが免疫力を高めることも、科学的に証明されています。
私たちも、親しい人と会話したり、自然の中に身を置くと、心が安らぎますよね。リラックスして過ごせる空間は、心身ともにすこやかにしてくれます。
家にいながら健康に近づける
二つのポイントとは?
ところで臼井さんは、マンションから一戸建てに引っ越したそうですね。住み心地はいかがですか?
――広くなったし、2階の窓から遠くの山が見えて気持ちがいいです。ただ、階段の上り下りが多くって、面倒な時もあります。
最近は階段のない、平屋の家が人気ですよね。
一方で、階段がない場所で過ごす=運動量が減るということ。使わない筋肉は、どんどん衰えていきますよ。
――確かに! 2階建てに住むようになって、足の筋肉は鍛えられている気がします。
ラクな空間がいいと思っていたけれど、これだけ家で過ごす時間が長くなると、運動不足にならないようにすることも考えないといけませんね。
家にいながらでも健康に近づく方法って何かありますか?

ありますよ。例えば2階建ての家だったら、1回で済む用事を何回にも分けて、階段の上り下りを増やすのはどうでしょう? 階段がない家なら、踏み台を置いて隙間時間に昇降運動をしたり、掃除機だけでなくたまに雑巾がけをしてみたり、無理なく運動量を増やせる仕組みを考えてみてください。
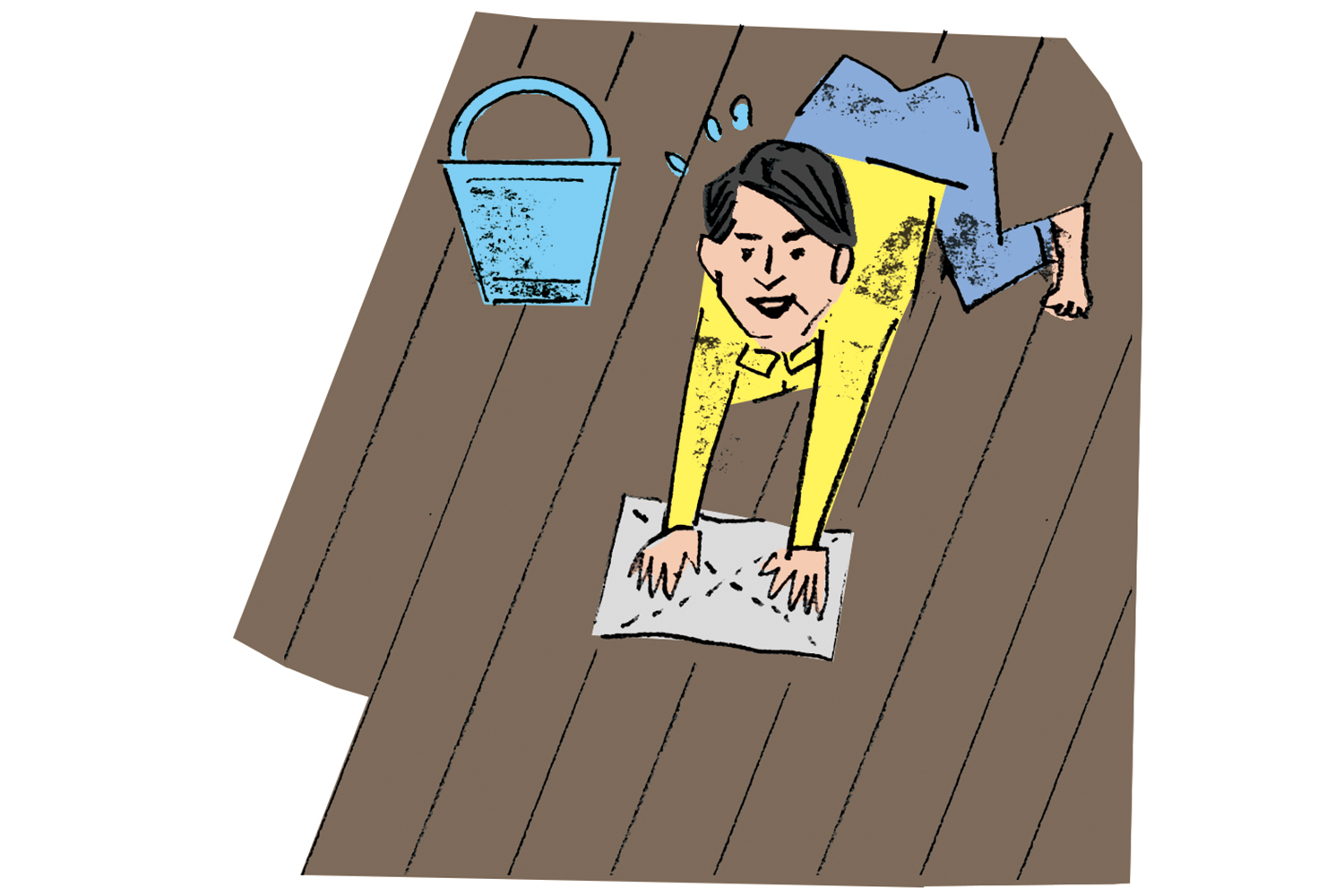
――ふむふむ。運動不足を防ぐ工夫ですね。
もう一つ提案したいのが、「家の中に、リラックスできる空間を3カ所以上つくる」ということです。
例えばリビング、ダイニング以外にもう1カ所、自分がリラックスできる空間をつくれないか考えてみてください。リラックスできる場所は、一つでも多い方がいいですからね。
椅子を一つ置くだけでも、空間が変わりますし、家での過ごし方も変わってくると思いますよ。
更新